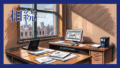Q.相続手続きの各処理段階でどんなことに気を付ければいいですか?
A.主だったポイントを3回に分けて紹介します。今回は5と6と7について回答します。
5.遺言書が無かった場合、又は 相続人全員の意思で遺言書と異なる遺産分割を行う場合、
遺産分割協議の実施、遺産分割協議書の作成
遺産分割協議を実施し、その協議で全員同意の分割案がまとまれば、その内容を遺産分割協議書として書面化します。
遺産分割協議で行政書士ができることは、弁護士法72条違反にならない範囲でのアドバイスです。
行政書士は協議同意のための相続人間の交渉行為はできませんし、しようとは思っていません。
因みに、遺産分割協議がまとまらないケースは、相続人がそれぞれの要望だけを主張する時のようです。
相続人が複数人いて、そのうちの一人の相続人が弁護士を付けた場合、
その弁護士は 誰のために働くのでしょうか?
弁護士法は、弁護士は依頼人のために働く旨、が記載されています。
弁護士法は、弁護士は相続人全員のために公平となるように分割しなければならない とは記載されていません。
相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合、
まずは、裁判所に 調停を求めることができます。
調停でもまとまらない場合は、審判の申立てができます。
知り合いの弁護士にきいた事ある話ですが、
弁護士が審判の代理人になったとしても、裁判所の審判では、法定割合に基づいた分割案が提示され、
弁護士費用がかかっただけ と弁護士が依頼人に嫌われることになることがほとんど とのこと。
弁護士を使えば 思う通りに遺産分割できるということはまず無いです。
相続できる財産が実質的に減っても構わない場合は、弁護士に遺産分割協議も頼んでもいいのかもしれませんね。
6.相続税の申告
遺産財産のすべてが明らかになったら、その額を金銭で評価します。
その金銭が一定額を超えたら、相続税がかかります。
相続税は、相続人が誰なのか? 相続される財産に居住建物が含まれるか? 等で変動します。
大まかに言うと、相続財産が3600万円を超えない場合、相続税はかかりません。
特に注意がけたいポイントは
相続財産には 死亡保険金が含まれる場合 と、含まれない場合 があることです。
死亡保険金が相続財産に含まれない と思って相続税申告しなかった場合に、
実は 死亡保険金を相続財産に含まなければならなかった場合、
税務署から未申告と指摘されたら、追徴課税を課される場合があるんです。
相続税の申告は、本人で出来ます。というより 本人がするべきです。
必ずしも 税理士に頼む必要はありません。
税金の計算方法は 税務署でしっかり教えてくれますので、
特例適用できる思う旨をしっかり税務署に説明して、税務署のお墨付きを貰えばOKです。
7.不動産等の登記を必要とする相続財産に関して 相続による所有権移転の登記
不動産を相続する場合は
本人が法務局に相談して下さい。
遺産分割協議書等を持参して 法務局に行けば、詳しく手続き方法を教えてくれます。
昔は、司法書士に頼め と上から目線の法務局職員も多かったですが、
最近の窓口職員は 丁寧な人が多くなった気がします。
つまり、必ずしも 司法書士に頼む必要はないんです。