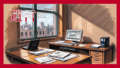遺言の種類は大きく分けると 普通方式遺言 と 特別方式遺言 の2種類で分けられます。
特別方式遺言(民法976条-民法979条)には
「危急時遺言(一般危急時遺言)」
「危急時遺言(難船危急時遺言)」
「隔絶置遺言(一般隔絶地遺言)」
「隔絶置遺言(船舶隔絶地遺言)」
の4種類があります。
特別方式遺言の特徴は、
口頭で遺言を残すことを認めるしかないような 危急の状態での遺言方法であることです。
民法976条 (死亡の危急に迫った者の遺言)に 以下のように規定されています。
1.疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、
証人3人以上の立会いをもって、
その1人に遺言の趣旨を口授して、
これをすることができる。
この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、
遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、
各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2.口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、
遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3.第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、
遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、
同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、
同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4.前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から20日以内に、
証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5.家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、
これを確認することができない。
簡略して言い換えると
1.遺言者に死亡の危急が迫り署名押印ができない状態の場合に
2.口頭で遺言を残し、
3.証人が代わりに書面化する
遺言の方式です。
制度としては保証されていますが、
実際に適用できるかは難しいので、
行政書士はほぼ扱わない遺言方式です。
今の時代で 災害に巻き込まれた本人ができる特別方式遺言の可能性は
スマホに 遺産分割案を本人が危急時に動画として残し、
そのスマホ動画が 何らかの形で遺族に伝わり、家庭裁判所でその心証を得る
ことかもしれません。
遺言2(特別方式遺言:種類と特徴)
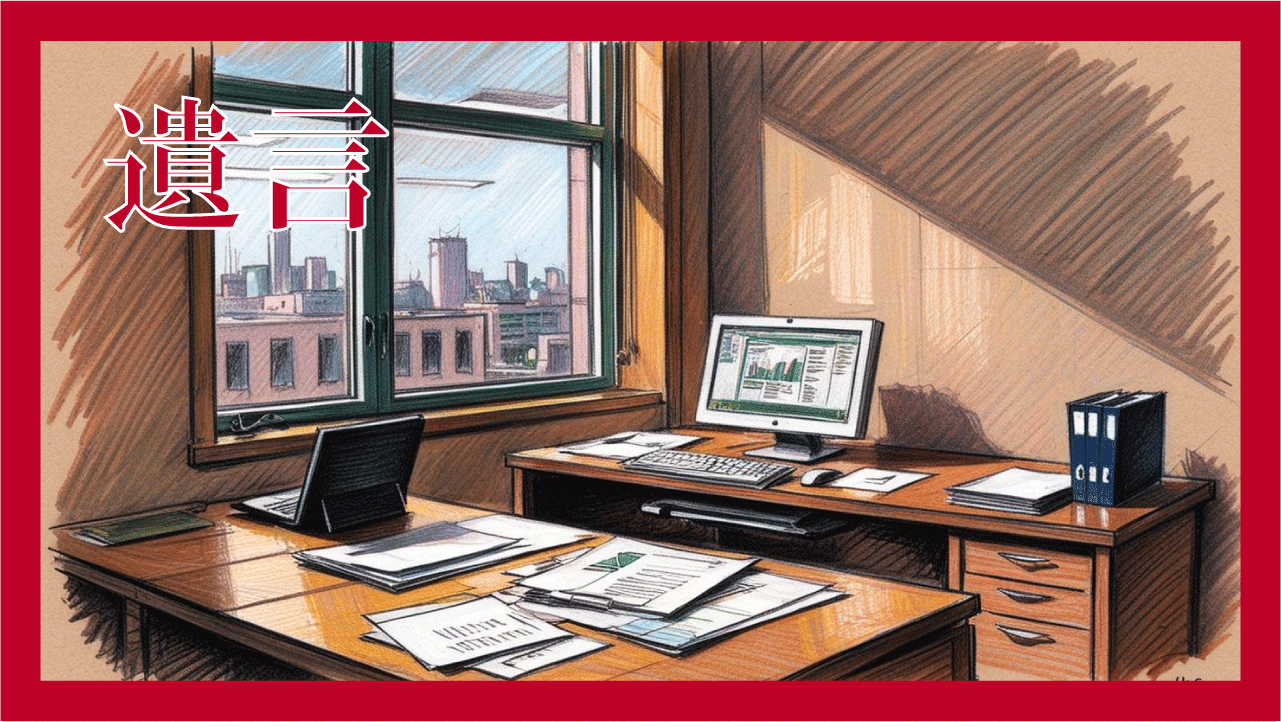 遺言
遺言